サイカイアトリー・コンプレックス 実学としての臨床
サイカイアトリー・コンプレックス
実学としての臨床
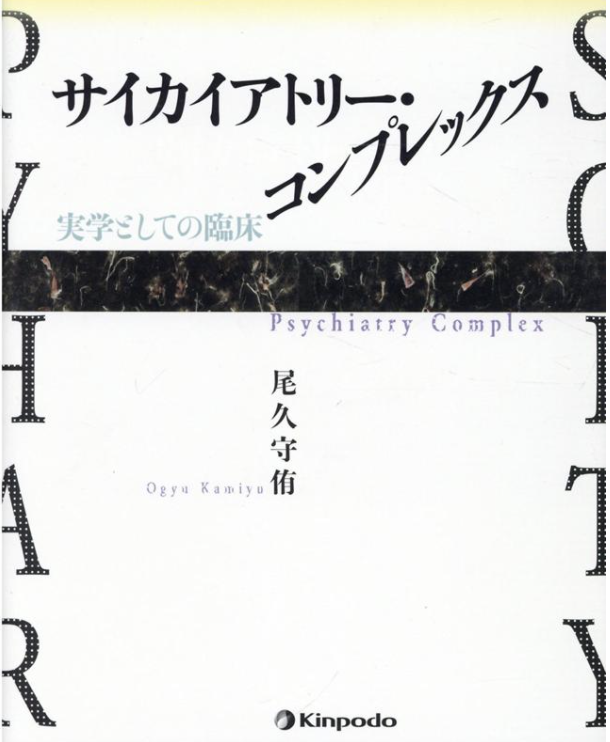
ニハクさんとTwitterスペースで読書会をするのですが、その書籍、『サイカイアトリーコンプレックス』について、私のメモシェアします。
精神科の先生が書かれた、「エビデンスばっかり見てるんじゃなくてちゃんとその人を見なさいよ。」という内容です。
ハウツーではなく、実学に基づいて尾久先生がどうされてるのかが実臨床とともに書かれています。
その中でもここちめいどとも繋がる事あるなぁと思ったので興味がある方は是非。※私としては、まずガイドラインを見てからその人を診る、という風に受けとったので、やはりガイドラインだいじ。
P.
しかし、どこか最近の傾向として、エビデンスや「●●理論」「●●モデル」といった一つの整った雛型を用いることで、この複雑系をコントロール可能と考える態度が猖獗(しょうけつ)を極めているように思う。
P.8 現場においては精神科医(もしくは病院)それぞれに「俺のうつ病」があるというのが実情です。
大脳に直接関わる診療科とか、全身疾患を扱う診療科の病棟では原疾患がうつ状態を引き起こすことは日常茶飯事です。なのでやっぱり医師にも病棟のスタッフにも、「うつ」を神経学的な内科的な症状だと捉えてよく習熟しておいてほしいなと思います。
P.13 非精神科医療従事者は基本的に「高齢発症の精神疾患」というものを疑ってかかったほうがよいように思います。よく「精神疾患が隠れているのではないでしょうか」という依頼をもらうことがありますが、「非精神科病棟」で「新規」に高齢者が「精神疾患」を発症してしまうなどということはまずないと考えた方がよいです。
P.14高齢発症の精神疾患…退行期メランコリー、遅発緊張病、遅発性パラフレニアなどと呼ばれる。
P.16「違うだろう」と思いながらも頭の片隅で「もしそうだとしたら」という可能性を100個も200個も並べながら、最も妥当性の高そうな仮説に「ひとまず」のって考えていくという行為が現場では大事だと思っています。
P.22教科書に書かれていない精神症状だから起こる確率は0%であると判断しないことが大切です。
P.26我々がしっていること、できること、というのはとても狭い窓から覗いた外の風景のようなもので、一歩外に出ると思ってもいないような論理で思ってもいないような出来事が繰り広げられている可能性だってあるのです。とにかくそこに自覚的であること、どこが境界線なのかを意識しないと、大きな間違いを犯してしまう可能性があります。
p.33 Bush-Francis Catatonia Rating Scale という基準は、典型的ではない緊張病を捉えるのに結構いいなとおもっています。
p.43 物取られ妄想、嫉妬妄想
p.45 SSRIの重篤な副作用の1つにセロトニン 症候群というのがあって、脳内のセロトニン 濃度が過剰になり、ミオクローヌスや振戦、筋強剛といった神経症状や、自律神経症状、意識変容(主に興奮や錯乱、軽そうなど)をきたします。
p.54「こういうこと言う人は自殺しない」という確信が、「こういうことを言っていたのに自殺未遂を帰りにされてしまった」という経験に基づいて、「こういうことを言う人の中には自殺しない人と自殺する人がいる」という考えになり、「その差はどこなのか」という目線に変わってくるわけです。常に微妙な「やりすぎた」と「やらなさすぎた」を往復する運動が臨床であり、これには終わりがありません。
p.57 薬を飲んだせいで認知症になってしまったようだ
高齢者の認知機能が低下しているとき、真っ先に考えるべきなのは意識障害ですが、医師を含むかなり多くの医療従事者が「認知症」としか認識しないということが頻繁に起こります。
さらに「辻褄が合わない言動」というカルテでよく見るアレがない高齢者は意識清明とみなされてしまい、私が「意識障害である」と書いたとしても謎の多数決というか場の雰囲気で「違うよね」みたいなノリになってしまいがちです。
「もう、学校とかでちゃんと教えてほしい。たのむ」という気分になります。
P.61頭部画像検査は必須です。できればMRIをとりたい。
p.68医師の目が曇る1つのわかりやすいモデルとして、「患者に精神疾患がある」「患者が向精神薬を飲んでいる」という状況があります。確かにこういう訴えで来て、結局便秘でしたとか、精神症状の悪化でした、みたいなことはしばしば内科外来では経験しますが、それっていつもの緻密な診療プロセスを経てないですよね。「精神科患者」「よく分からない訴え」というところで、ショートカットが発動してしまっている。
p.71病気のない高齢者夫婦の症例報告なんて誰もしないし、どこの雑誌も扱っていない。でも実際はMPO-ANCAが陽性になる人の何倍もそういう人たちはいるわけで、彼ら彼女らもまたどうように患者さんなんですよね。症状があるのに病気がない人はみなくていいというのは、気分に論理を従わせているだけなのではないでしょうか。こういう人をみるときに、「誰かが“損”をしないといけないなら自分が“損”をする」というマインドになると急に診る気がしてくる人と、「こういう人の症状はどうすればよくなるか?」というマインドになると急に診る気がしてくる人と、いずれにしても理屈をつけてみないといけない。精神科にうまくつなげられた人はいいとしても、うまくつながらない人は「一体どうしたらいいんや」となるのも無理ないです。現実的な言葉で話すことが困難になっていて「つらいという雰囲気」の世界に住んでいます。よって、症状がよくなっても、自分の内部に出現してきた症状がよくなったという感覚に目が向かず、かなりの時間はよくなったと表現できないことがほとんどです。
本人の訴える内容ではなく、行動であったり表情であったりの変化を治療評価の指標とすべきです。
看護師「本人はああ言ってるけど結構いいですよ」みたいなことを言ってくれる事ありますよね。特に「痛み」のある人では必須の概念なのではないかと思います。痛みが0にならないとずっと10と言い続けるタイプの人がいますが、あれです。
p.76非治療場面におけるコンタクトは一律してもたないというのが境界侵犯を防ぐという意味では最も安全です。例えば精神科では多重関係(患者医師関係以外の関係を持つ事)を避けるのであまりないかもしれません
p.78 「俺がなんとかしてやろう」となりがちな医師が手を差し伸べると、溺れるものは藁をも掴む的な感じでもっともっととその手をつかもうとし、このままじゃ自分も溺れてしまうと青ざめた医師がその手を振り解くと、余計に事態がこじれるということ、まあありますよね。p.79こういう人はむしろ本人のコントロールできる部分を増やす、という方向に構造を作っていくべきだとおもいます。
p.82 「先生薬の調合ヘタクソだね」とムカついたときは、俺は自己愛が傷ついてむかついているんだなぁ、とちゃんと自覚することが大事です。
この人はいつもさらっと終わってしまうなということを自覚すること。患者の病態だけを考えていると、思わぬ失敗をする事があります。自分の患者の病態に影響を与え、与えられている存在の一人なんだと自覚して診療に取り組む事。
p.90 自然界がデジタルになっているはずがないのですね。グラデーションになっているわけです。まずこの普通の事実を再認識します。
p.92 私は診断というのは「風味」でするのが真実に近いと思います。これは内科疾患だろうが、精神疾患だろうが同じです。診断基準などというものは、自然現象で集合しているかたまりに外界からマジックで線を囲ったものにすぎません。
p.96 表出が精神症状であろうが、神経症状であろうが、その他の身体症状であろうが、何はともあれ身体の病気だと思ってまずは診る事が大事です。p102当然脳内で屈折率を補正しながら患者の話を聞いていかないと、適切な診断にたどり着く事ができません。
さらには、本人の訴える自覚症状と病態がどうも合わないときなどに「あなたのいう下痢ってどういうことですか?」などと尋ねることで、本人の行っている「下痢」とこちらのイメージしている「下痢」が違うことに気づけたりします。
p.111 あなたのいう怖いというのはどういう感覚なのですか?
p.116 最近では精神科においては操作的診断基準というものが猖獗を極めており、これはこれこれこういう症状が何ヶ月続いたら何病ですと考える診断基準で、臨床研究に患者を組み入れるときに条件を揃えるという意味では、そういう決まり事が必要なために私も使っています。
p.126 bipplarity + 自由の制限 →うつ は、最も基本的な立式の1つです。
p.132精神症状ってそんなに特殊ですかね?
p.135 「依存的」なのは「うざい」とか「精神科コンサルタント」ではなく、「病態」であると認識しましょう。
p.143 「臨床は誰がやっても同じ」とか、「ガイドラインに従わない=とんでも医療」とか思っている人にとっては理解不能というか、ふざけた弾糾すべき考えに映るかも知れません。
しかし、「ガイドラインがあればそれでいい」わけではありません。それに居ついてはいけない。
p.146 だんだん、すべての内科疾患は心身症なんじゃないかという気になってきます。
まず「どれがメインの疾患による症状で、どれがその最初の症状に反応して出現した症状か」を見分けるという発想です。
p.150 ①が実は整体で解決するような方の器質的な痛みで、その症状から不安が出現し、②の各種自律神経症状が出現したというパターンです。
p.152 また、①の根本治療でなくとも、①が元疾患による「痛み」だったりする時、②は「原疾患」ではなく「痛み」によって起きているわけですから、痛みをとるだけでも①②も消えるという現象が起こることがあります。
p154 ①が「痛み」で、ここに「処方なし」という事実が加わった結果、「何もしてくれなかった」などと被害的な感覚が強まり「怒鳴る」という②の症状が出現します。
痛みがなくなれば、怒りも引いていくわけです。なんだが当たり前のようですが。
p.159 診断基準を満たさないからといって、その要素が「ゼロ」と考えるのは科学がどうこうではなく端的に誤っています。
p.162 打撃は「部活の顧問と合わない」「上司によるパワハラ」「身内の介護が必要になった」といった、容易に除去できないことなので、そこはいじれないことが多い。
本人が納得できるかというところが全てになると思います。
p.164 やめられるのだったら、みんなやめているわけです。だから「問題行動」とみる前に、どうして「酒浸りにならざるを得ないのか」ということに思いを巡らせてほしいです。
p.166 実際何でよくなっているかなんてわからないですからね。診察室でお会いする患者さんというのは本人の全体の生活からすれば氷山の一角で、語っていない重要な情報のほうがむしろ多いと言えると思います。すべてを把握していなくても、わずかでも本人がよい方向に向かえる手助けができればいいなと思っています。
p.168 精神症状や検査異常がどう考えてもない身体症状の人との関わりは、「会話」と「薬物」によってなされます。
関わりの技術もあげていきたいですよね。
p.170 この「こういう感じ」が定量しがたい。
ただ機械的に薬を出すだけではうまくいかない人というのが必ずいます。つまり、関わりが必要な人です。逆に言えば、薬の力はほんの少しで、関わりだけでほとんどよくなる人というのも数多くいます。かかわりでかえでよくするということです。
p.175 「薬を処方している」という発想を転換し、「医師としての一挙手一投足を処方している」という考えを持つ事です。
p.176 まず患者さんから発せられる「そうじゃないんだよ…」というメタメッセージに敏感になりましょう。
p.181 こうして読み返すと、自分発の発想というのは何1つないのではないかという気がしてくる。どの考えも、伝統の蓄積の合間から滲み出してきたものであり、内面化してしまっているために、どれが人の考えて、どれが自分の考えかわからなくなってしまっているというのが事実だ。


